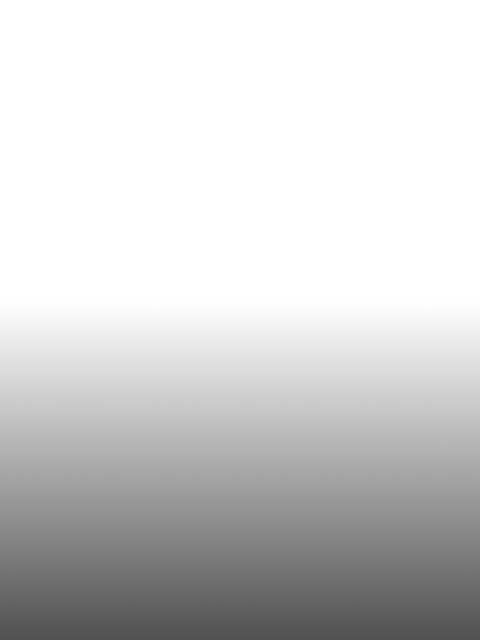田原総一朗が「ドキュメンタリーでは描けない菅乃監督の憤りが痛いほど感じ取れる。』とコメント。現在公開中の四世代にまたがる家族の物語『あいときぼうのまち』。今、監督の菅乃 廣、脚本の井上淳一 のメッセージが熱い… 。
監督 菅乃 廣
「愛と挫折の物語」
2011年3月11日の東日本大震災で被災し、これに誘発されて3月12日に発生した、福島第一原子力発電所で、1号機と3号機が水素爆発。3月19日以後は、原発事故の影響を受けて住民の避難が必至となり、約1,200人の被災住民は役場の機能ともに避難。以降、立入禁止区域に指定、死の町と化しています・・・。
私の出身地は福島第一原視力発電所から50~60キロ離れた場所です。避難地域には指定されていません。町の人は、普通の生活をしています。しかし、植物が巨大化するなどの異常に不安を感じながらも、安全だという政府の情報を信じて平静を保っています。そして政府は、経済成長のため原子力発電の海外への輸出を推進する・・・国家がしきりに強調する「安全」という情報に翻弄される人々・・・第二次世界大戦中、「日本が戦争で有利になっている」と国民を思いこませた国家による情報操作・・・組織の利益が優先され個人が犠牲になる社会・・・戦争に突き進む狂気と、未だに原発に執着する狂気・・・基本的な日本の構造は、第二次世界大戦から70年たった今でも、何ら変わりがないのではないか・・・。
過去の因果が次の世代に影響を及ぼし、その時の因果が更に次の世代に影響を及ぼす・・・ウランの核分裂の際に起こる連鎖反応のように、過去の因果が伝播していく・・・このような手法で表現する愛と挫折の物語です。
脚本 井上淳一
「忘れてはいけない、だけど、赦してもいい」
たぶん、あの日を体験した表現に関わる者の多くが、これからは否応なく「3.11」後を意識せざるを得ないし、意識しない作品に何の意味があるのだろう、くらいのことは思ったはずだ。もちろん僕もその一人だった。しかし、実際に3.11モノの仕事が来た時には迷った。もう少し正直に言えば、イヤだった。理由は二つある。その仕事が来たのは、2011年の晩夏。あの日からようやく半年が過ぎようかという頃だった。まだ半年。表現に足るほど、僕の中で3.11も3.11後も熟してはいなかった。ただでさえ、実際に被災した方の側に立つのは難しい。果たして自分はその痛みや喪失感を想像し、表現できるのか。いや、そんなものが表現可能なのか。それをクリアしなければ、3.11モノなど作る意味などないし、雨後の筍のように生まれてくるであろう、その手の作品の中に埋もれてしまう。それが、ひとつ。もうひとつは、いくら論を重ねようが、映画を作るということは商売をするということだからだ。お金を儲けることを良しとするに足る、表現すべきものが果たして自分の中にあるのか。
しかし、僕は書いた。その結果は、作品を観て判断していただくしかないが、それでも、この作品を書いて良かったと思うことがある。シナリオを書き上げたのは2011年の年末だが、その時点でさえ、3.11直後は暗かった東京の街は明るさを取り戻し、震災も原発もその一年を振り返るニュースの中でしか取り上げられることがなくなっていた。そして、三年。都知事選で脱原発は争点にならず、五輪招致のスピーチでダダ漏れの汚染水を尻目に「福島はアンダーコントロール」と平気な顔でうそぶき、原発再稼働に邁進する首相の支持率は未だ高い。人は忘れる生きものである。その中でも日本人はことさら忘れやすい生きものなのか。被災地と我々は地続きである。そして、過去からの時間もまたずっと続いている。福島になぜ東京に電気を送るための原発が建てられることになったのか、我々はそれを忘れてはいけない。最低限、そのことだけは語ることができたのではないかと思っている。
最後にタイトルについて。この作品は大島渚監督のデビュー作にして傑作『愛と希望の街』(1959)を平仮名にしたものだ。大島渚は当初、階級差は決して埋まることはないというテーマのこの作品を『鳩を売る少年』と名付けていた。しかし、会社から反対され、大島は反語的にこのタイトルを付けた。だから、実際に映画の中で描かれている世界は「愛も希望もない街」なのだ。この映画のタイトルを付けるとき、どうしてもこれ以上のものは思い浮かばなかった。平仮名にしたのは、55年前よりいまの方がより問題がよりソフトになり見えにくくなっているのではないか、と思うからだ。ただ、それだけではない。やはり、「あいもきぼうもないまち」にではなく、「あいときぼうのまち」に住みたいと僕は思う。それは、この作品の底に流れる、忘れてはいけない、だけど、赦してもいい、という祈りにも似た願いに通じている。
そして、もうひとつ。昨年は大島渚が、一昨年には新藤兼人と若松孝二が死んだ。いま、この三人が座った席がポッカリ空いている。いま、このような時代になり、その席に誰かが座らない限り、席そのものがなくなってしまう可能性が高い。僕が座れるか否かではなく、誰かがエントリーしなければいけないと思う。そういう意味においても、このタイトルを付けたことは間違っていないと信じたい。
シネフィル アジア


 *REVOLVER
*REVOLVER