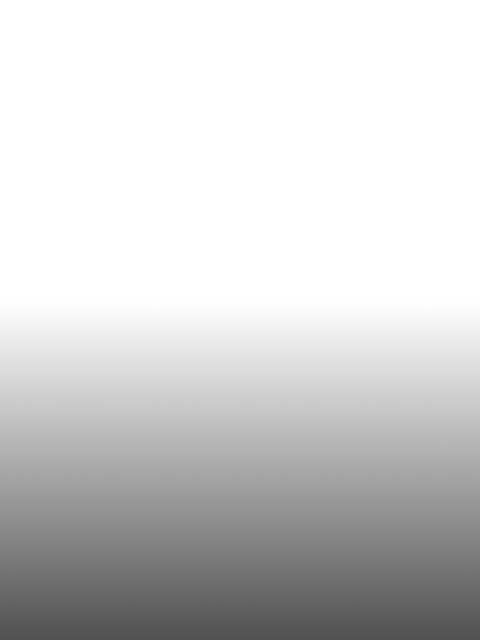犬童 一心 監督 、『映画の奈落 北陸代理戦争事件』 伊藤彰彦著を読む
犬童 一心
7月6日
『映画の奈落 北陸代理戦争事件』伊藤彰彦著を読む
映画の製作が最中にあった抗争を激化させ、実録映画さながらの銃撃事件、殺人事件が起きていたということを初めて知った。この本は、おもしろい映画を観ているように面白い映画本だ。
映画本の面白さのひとつにはやはり映画のようにおもしろいという所があるんじゃないだろうか。人が、人の行動がこちらの想定を裏切って行くこの本の面白さはまさに良いときの実録ものの面白さだ。そして書き手の構成力の素晴らしさはまさに優れた脚本家のそれだ。
封切りで観た最初の実録ものは75年の『新仁義なき戦い』だった。下高井戸東映で正月に観た。それが中学二年。高二で『北陸代理戦争』を観るまでの間、随分と面白い東映作品たちに出会った。
75年はすごくて『仁義の墓場』があり『新幹線大爆破』があり、『トラック野郎』がありという年。『新幹線大爆破』を封切り初日に行ってがらがらだったとき、中学生ながら東映はつぶれるんじゃないかと心配になった。
ルート66の日本版を作りたいという深夜放送で聞いた愛川欽也の言葉を信じて『トラック野郎』も封切りに行った、ルート66とは全く違いながらひたすら笑えて。「ああ、なんてくだらなくて最高なんだ」と思った。劇場も満員でホッとした。
『仁義の墓場』のとんでもなさにはほんとにまいった。暴力性が限界を超えて観ていてつい笑っちゃう経験は『悪魔のいけにえ』とともに(同じ頃の封切りだった)その後の映画感に多大な影響を残した。
77年の『北陸代理戦争』は大変な迫力を有した優れたアクションものでありながら、殺伐とした物語と寒々し風景に何かある種の終末感を感じた。確かにその頃は実録ものに少し飽きていたと思う。
その前に観た『日本の首領』にがっかりしたこともあったかもしれない。アクションではあるが暴力を描くからこその面白さに疲れて来たのかもしれない。
この本を読んで、あの時あの作品を観て感じた殺伐とした感触が何処から生まれて来たのかがわかった気がする。いろんなことが終わろうとして、そして、新しく生まれる苦しみに最中にいたということか。日本映画は変わろうとしていた。
そして、松方弘樹の激しさよりもいまだに寒々しさの中にある野川由美子と高橋洋子の肌の温もりのようなことばかり覚えている理由もわかった気がした。
シネフィル アジア


 *REVOLVER
*REVOLVER